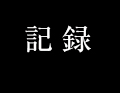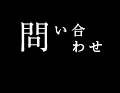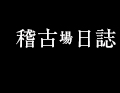4月, 2014年
「井筒と水月見」 更新日: 2014年04月01日
「井筒と水月見」
ご来場いただきありがとうございます。
舞台の今宵は中秋の名月です。飾り団子を供えます。
ラディヲからレゲエ・Bob Marleyの「redemption song」が静かに、あなたになつかしそうに聞こえています。
ご存知のようにというのも憚られますが、この公演の『井筒』というタイトルは世阿弥の謡曲『井筒』から借り受けました。舞台がそうなのかまた違うのかは観ていただくしかないのですが、ここでは「井筒」への思いや、いかほどかの「井筒」への距離を綴ることで、未知座小劇場やその舞台等々の紹介になればと思います。
少々、まだ戸惑っています。それは……
歌舞伎や文楽、能楽、あるいはシェイクスピア劇の舞台に接する機会がままあるのですが、そのとき、その舞台の内容や展開は、図書館や街の大きな本屋で事前に情報としていかほどかを得ることができます。多くの方が労するまでもなく、生活の中で気にかけてしまうこともあったりします。たとえば『曽根崎心中』といった具合です。
これらの舞台をここでの脈絡から、その歴史性や文化性、あるいはそれらに付された古典といった概念を割愛して、その情況を再演という上演形態、そのような物言いを被せて集約できるものとします。そこに事前に情報が成立するという場の一つがあると思われます。ですが未知座小劇場には再演という意思はありません。傲慢にも観ていただくしかない、と綴ってしまわざるをえません。そうして……戸惑ってしまいます。
ともあれ、多くを囲い込むことは可能です。
ここでは『井筒』に焦点を絞ることから始めます。世阿弥の謡曲に、わたしの関心がある部位は次のように記されています。
ことによっては少々複雑な構図になってしまいます。「業平」と「業平の面影」の差異であるといい始めてもいいように思われます。謡曲では井筒を覗き込む後シテ・井筒の女が井筒の底の水面に「業平の面影」を見ているということにもなるのではないでしょうか。
このわたしの断定はやはり傲慢です。「井筒」を私物化してしまうからです。井筒の底は、演劇的に開かれることで、想像力は解放される。ですがここでは「業平」を見ているのではなく「業平の面影」を見ると地謡でいい定めているのだとも、誤読します。わたしは、後シテ・井筒の女が「昔男の、冠直衣」をまとうことによって「業平」のようであるということを、単に井筒の底の水面にまで引き伸ばしているだけなのかも知れませんが、それはわたしだけの独断で了わるのではない、といえるのではないでしょうか。この事態はそのようにも読むことができると思います。
さてすると、次のような物言いは可能でしょうか。業平の形見をつけて前シテ・里の女が井筒を覗き込むことで、後シテ・井筒の女は成立し、後シテ・井筒の女は前シテ・里の女と業平を見ているのだ、と。
換言すれば「業平の面影」とは自身のことであり業平のことだと。ここまでは想起されます。それはつまり業平が業平を覗き込んでいる。里の女が里の女を覗き込んでいる。このトートロジーは同義反復ではなく自家癒着といったらいいのでしょうか。追憶という時なのかも知れません。
こうして井筒の下の水面は、わたしには近代主義的な自我をうつす鏡である、ということができます。鏡ならただ佇んで魅入るのでしょうか。ここは舞台ですから、その佇みをあなたが観客席から見るというのであれば、見ることが見られることだという無限連鎖が、終わることのない見る=見られるという入れ子が成立するのでしょう。そのときあなたは、客席に在りながら、井筒の底で月明かりに照らされているということにもなります。
これは見るものが見られるという近代劇の構造です。能楽の『井筒』がそうでないとするなら、わたしたちはついに里の女の寂寞と憐憫を、それらを甘受するものがあってしまうそのような大いなるものに立ち会わざるをえないのでしょう。ここまでくれば、わたしはついに「曰く不可解」と斜に構えてポーズします。このポーズを突き崩すには、やはり『古事記伝』をあらわした本居宣長がいう「物のあわれ」に類するものを持ち出し、それを「ありのままをありのままに受け入れる心もち」とすることで、突き崩せるのではないかと考えます。
二〇一四年の現在に生きるわたしたちはさらに、現代のわたしどもの語感からこの事態をみれば、拡散しながらこれを宗教的に概念化してみれば、里の女は親鸞のいう往相回向を願い、在原業平を受け入れるべく、浄土から還相回向をはたしてあるべく、ここにいる。そのこと自体が里の女の往還回向です。こうして「井筒」は浄土へのとば口であり、振り向くことのない出口となります。親鸞は大無量寿経十八願のはて、里の女は仏(=井筒の女)となって往還をはたしここにいるのだというかも知れません。そのような誤読を許すかも知れません。わたしは『歎異抄』をそのように読みます。
あくがる……『源氏物語』に出てくる言葉を使えば、里の女はあくがれてあると思います。
さてではこの世界は、どのようにいったらいいのか、それは舞台ではいかにして可能かという仮設は、演者が男であり、シテの役柄が女であり、さらにそのシテの女が業平という男を行為するという能楽の構造のなかで「井筒」を「井筒」たらしめているのだろうと、そう言葉でやはりいってしまいます。ですが、これらをわたしが思いつくままの構造として提出したとして、未知座小劇場の稽古場の俳優には何程の助言にもなりません。このような物言いはフムフムと聞くしかないのです。仮設が捏造されるということと、場の行為がそこにあってしまうことは、まったく別の可能性です。
ともあれ、まずこれらの仮設を加算法と呼んでおきます。
構造を身体として構造たらしめるには、控除が問題です。引き算です。例えば歌舞伎の女形が、女を行為するのではなく、男を消すことであるとするなら、これは構造としての控除法です。逆説が許されるなら、何もしないということが、在るという行為なのかも知れません。言葉を弄んでいるのだとしても、道元の只管打坐や百尺の竿頭は、浅はかにも、わたしにはそのようにしてようやく想起されるだけなのです。今はそうなのだと吐露するしかありません。
だがしかしさて、今回の未知座小劇場の『井筒』に出演するのは女優三人のみです。
この女優三人のみというのはもう一つの枷をはめただけという加算法になるのでしょうか、意味ある控除法を引き出すのでしょうか? いずれにしろ、何を行為しないのか。大それたことをいえば、演劇が演劇であってしまう身体は、いくらかの呟きをもらすでしょうか?
いまひとつ、この場でこういう問いが許されるなら、「業平の面影」の本当とはなんなのでしょうか。どこまで持ち運べば、後シテ・井筒の女の世界はすべてを凌駕して、世界に屹立するのでしょうか。わたしが、あの場で立ちつくしたのは何であったのか?
一般的に、無難にいえば繰り返しになりますが、井筒の底の水面には「近代的自我」があったのでしょう。多分、水面という鏡です。わたしたちは自身を他者という鏡にうつして自己を確認します。そんな「近代的自我」です。他者を認めることで自己を定めるはずです。中世史家の網野善彦に習っていえば、これらの現在のわたしたちの生活心情や価値意識は中世までは通用し、持ち運ぶことができるとするなら、ここでの世阿弥が仮設した「近代的自我」がその始まりであったということができるのではないでしょうか。このことを換言すれば、この「井筒」が夏目漱石の『門』であるとすれば、そこに入ることも、またいることも受容できないわたしという自我が「井筒」(=門)をでて歩き始める、ということになるのでしょう。
まだ多面に拡げてみます。
思いつくままに想起すれば、この「井筒」の底の不気味さと、わたしの立ちすくむという驚きは、やはり柳田國男の『遠野物語』に似ています。山人譚に類似します。この「井筒」自体が境界という意味で道祖神ともいいたいほどです。すると、金春禅竹の『明宿集』にならうなら、この「井筒」の底は「後戸」ということにもなる。またそこには折口信夫の「まれびと」が現れるのかも知れません。いくところまでいけば、能にして能にあらずの「翁」の世界にたどり着くかも知れません。
総じてここには物語が横たわっています。安藤礼二はこの『遠野物語』のことを「私と共同体、声と文字という通常では乗り越えがたい差異を無化してしまう作品なのである。そこに紡がれる物語も、生者と死者をつなぎ、現実と超現実をつなぎ、現世と他界をつなぐものとなる」(『たそがれの国』)と。物語といえば中上健次のことを思い出します。中上健次は『千年の愉楽』で「路地」を物語として提出していました。きっとこの「井筒」は路地に通じ、迷宮の扉をあけることになるのでしょう。
こうして、この「井筒」は物語のとば口と思われます。
視点を変えます。わたしども未知座小劇場の『井筒』には西行法師がそれとなく登場します。名づけて「西シャン」です。わたしが口ずさむ西行の歌に次があります。
この「心なき身にもあはれは知られけり」と後段の「鴫立つ沢の秋の夕暮れ」の飛躍といったらいいのか断絶といったらいいのか、バリエーションの差異としないこの移行はなんなのかと考えてしまいます。寺山修司の「マッチ」と「祖国」ともかけ離れて異なるものです。その離れさ加減に魅入ってしまいます。井筒が、この廃寺のここに在ってしまうという断絶です。
もう一つ処理しきれないものがあります。
井筒の底に空海がいます。そこから観る月明かりは、室戸岬の御厨人窟のように差し込んでいたはずです。ここで私度僧空海の口に、ついに明けの明星が飛び込む。そんな井筒の底です。
世阿弥の『井筒』に深入りせず、わたしどもの物語に近づけようとしたのですが、さてなにほどか世界を想起する囲い込みはできたでしょうか。そうしてやはり多分といいたいのですが、すでにお気づきのように、わたしはこの拙文で「井筒」を、多くのイメージを羅列することでそれを無化しようとしたに過ぎないのではないのか、と最後に呟きます。
多くは乱反射したままである、といいたいほどなのです。 さて、こうして未知座小劇場の『井筒』という物語は、とある四畳半のアパートの一室で繰り広げられることになります。書き忘れてしまいましたが、そこは唐十郎の『少女仮面』、ジャン・ジュネ『女中たち』や三島由紀夫『サド侯爵夫人』の一室でもあるはずです。
ラディヲからBob Marleyの「redemption song」や桂銀淑の「すずめの涙」が今夜も少々うるさく流れています。未知座小劇場の前作『大阪物語』が繰り広げられた一室に……
「……ラディヲを消してくれ!」
今回の舞台のように思いを乱反射させてみました。
みなさまには舞台をお楽しみいただければ幸いです。(文責・河野明)